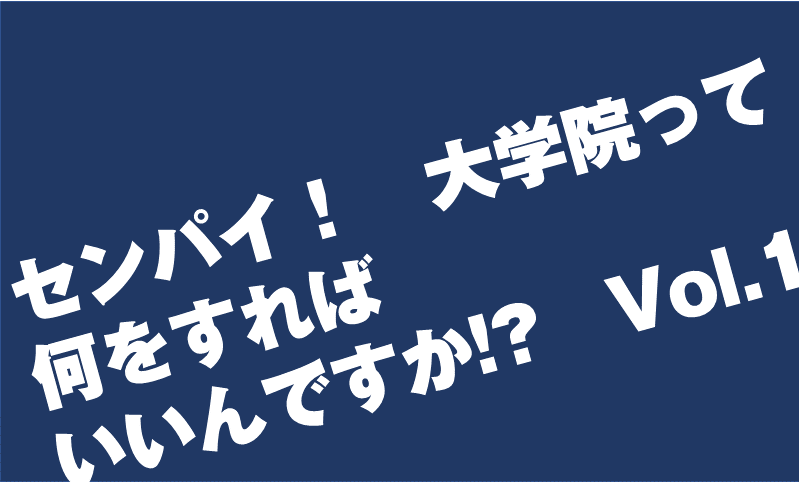ソーシャル・メディアをめぐる冒険 第12回 指導例「新しいメンバーを歓迎できる」

【連載】ソーシャル・メディアをめぐる冒険〈毎月第4金曜日更新〉
第12回 指導例「新しいメンバーを歓迎できる」
日本語教師のみなさん、こんにちは。冒険家の村上です。ただいまチューリッヒの空港でこれを書いています。
先月は Facebook などのSNSで自己紹介することができるようになるための指導案をご紹介しました。今月はこうした新しいメンバーによる自己紹介を見たときに、どのように歓迎するかを考えてみましょう。
今月の能力記述文
「オンラインコミュニティで、簡単な自己紹介であれば、短い歓迎のコメントで返信することができる」
index
ごく簡単な歓迎メッセージ
これができるようになるためには、コメントを返信する前に、相手の投稿が自己紹介であることが認識できなければなりません。しかし、これに関しては先月の記事で自己紹介を投稿する方法についてご紹介しているので、それはすでにできると仮定した上で話を進めましょう。端的にいってしまえば、「はじめまして」と書いてあれば自己紹介だと認識してしまうこともできます。
こうした自己紹介に対して歓迎の意を表するのは、実は自己紹介よりはるかに簡単です。なぜなら自己紹介のときは最低でも名前や職業などの何らかの自分に関する説明が必要で、それは他の人とは違う内容であるはずなわけですが、歓迎する場合は「ようこそ!」という一言だけでも用が足りてしまうからです。
つまり、オンラインコミュニティで新しい会員を歓迎するには、「はじめまして」という文字列を見たら「ようこそ!」と返信するというだけでもいいのです。とても簡単ですよね。もしかしたら、「それだけの短いメッセージに意味があるのか」と疑問に思う人もいるかもしれませんが、実際には活発なコミュニティではこうした短い歓迎の挨拶が何十個も返信されるようなケースがよくあります。そのコミュニティに入ったばかりの新しいメンバーにとっても、その数によって圧倒的な歓迎の気持ちを受け取ることができますし、多くの人がもっと長い歓迎の返信を書いたとしたら、それに対してまたお礼を書かなくてはならなかったりするので、ある意味新しいメンバーにとっても負担の少ない歓迎の挨拶ということができるでしょう。
長い歓迎メッセージを書くための5つのストラテジー
では、学習者がもう少し日本語の勉強を長く継続している場合はどうでしょうか。あるいは、あまり活発なコミュニティではなくて、他に歓迎する人が期待できず、もう少し長い歓迎の挨拶を書きたい場合はどうでしょうか。この場合は、もう少し戦略的な考えが必要になります。
1.相手への関心を示す
まず大切なことは、相手への関心を示すということです。そのためには相手のプロフィールを見たことがわかる歓迎の言葉にすることが効果的です。なかでも、いちばん簡単なことは相手と自分の共通点を見つけてそれを知らせることです。
- 例1:ようこそ! 僕もベトナムに住んでいたことがあるんですよ。
- 例2:ようこそ! 「進撃の巨人」、面白いですよね。
たとえば、以下の投稿は、この連載でもよくご紹介しているFacebookの「日本語」というコミュニティでハンガリーの日本語学習者がハンガリーに住んでいたことのある日本人に向けて返信したものです。
- 例3:〇〇さん、カバー写真がとてもきれいですねえ。あの ふうけいは ハンガリーのヴェスプレームの 「ベネデク」丘(Benedek Hill) ですか?
実は、このコメントは自己紹介に対する返信ではなかったのですが、相手がカバー写真に使っている風景を自分が知っているということを知らせることは、相手にそのコミュニティに対する親しみを持ってもらうのには大きな効果があると思われます。
2.一言付け加える
共通点はなくても興味があることが書いてあれば、それを一言付け加えるだけで歓迎の気持ちを伝えることができます。
- 例4:ようこそ! エジプトにいらっしゃるんですね。いちど行ってみたいです。
- 例5:ようこそ! ピアノが弾けるんですね。うらやましいです。
なお、FacebookなどのSNSでは、自分のプロフィールをどこまで公開するかはすべて自分で決めることができます。プロフィールの内容もそうですし、その共有範囲も自分で細かく設定することができます。新しいメンバーのプロフィールを見ることは完全に相手の選択の結果であって、個人情報を盗み見ているわけではありませんので、遠慮する必要はまったくありません。もしかしたら、見られて困る情報をそうとは知らずに公開してしまっている人がいるかもしれませんが、それについてはプロフィールを見た人の責任ではないのです。ただ、新しいメンバーのプロフィールを見る前に、投稿された自己紹介の文章の中に自分との共通点や興味のあることが書いてあれば、まずはそれを話題にするほうが無難ではあると思います。
3.質問する
先ほど述べましたように、多くのSNSでは自分のプロフィールの共有範囲を詳しく設定できますので、なかにはその人に関する情報がまったくなく、話の接点を見つけることが難しい場合もあります。その場合は、そのコミュニティのトピックに沿った形で質問をしてみるといいと思います。たとえば日本語を勉強する人たちのグループだったら、「どうやって日本語を勉強していますか」とか、アニメファンのコミュニティだったら、その新しいメンバーの好きな作品や作家等について質問してみるのもいいのではないでしょうか。
4.自己紹介を書く
「ようこそ!」という歓迎のメッセージのあとに、自己紹介を簡単に書くという方法もあります。詳しくは先月の記事で書きましたが、やはりコミュニティのテーマに沿った自己紹介が自然です。サッカーの好きな人たちのコミュニティだったら、自分の好きなチームとかプレーヤーの名前を書くのもいいと思いますし、アニメファンのコミュニティだったら自分の好きな作品や作家について書くのがいいでしょう。ただし、対面での歓迎の挨拶とは違って、ソーシャル・メディアでは自分の名前やハンドルネームが表示されていることが多いので、その場合はわざわざ自分の名前を自己紹介として書かないことも珍しくありません。
5.行動を呼びかける
そのコミュニティでよくある代表的な行動を呼びかけたりする例もよく見受けられます。たとえば、日本語を勉強する人たちのコミュニティなら、「ここで日本語を一緒に勉強しましょう」とか、「よくわからない日本語を見たらここで気軽に質問してください」などです。
いうまでもなく、こうしたストラテジーは独立して使わなければならないわけではありません。複数のストラテジーを1つの返信のなかに応用することもまったく珍しくありません。実際には、以下のような例もあるでしょう。
- 例6:
ティナさん、ようこそ!
カナダにいらっしゃるんですね。
どうやって日本語を勉強しているんですか。
よくわからない日本語を見たら、ここで気軽に質問してください。
どうぞよろしくお願いします。 - 例7:
マハムードさん、ようこそ!
エジプトにいらっしゃるんですね。いちどピラミッドを見てみたいです。
エジプトの観光地のことをたくさん投稿してください。
どうぞよろしくお願いします。 - 例8:
フオンさん、ようこそ!
イラストが上手ですね。うらやましいです。
私も『進撃の巨人』を全部読みました。
好きなキャラクターは誰ですか。
ここでたくさん日本のアニメについて話しましょう。
どうぞよろしくお願いします。
指導例
こうした例文を使って大量のインプットを行う授業の方法については、たとえば以下のような方法があります。
1回目:特にタスクを与えずに聞かせる。
2回目:「新しいメンバーの名前は何ですか」(必要なら媒介語も利用)
- 例6:フオン、ミカサ、マハムード、ティナ
- 例7:フオン、ミカサ、マハムード、ティナ
- 例8:フオン、ミカサ、マハムード、ティナ
3回目:「どんなコミュニティですか」(必要なら媒介語も利用)
- 例6:アニメ、旅行、日本語、スポーツ
- 例7:アニメ、旅行、日本語、スポーツ
- 例8:アニメ、旅行、日本語、スポーツ
4回目:「新しいメンバーはどこにいますか」(必要なら媒介語も利用)
- 例6:エジプト、ベトナム、カナダ、わからない
- 例7:エジプト、ベトナム、カナダ、わからない
- 例8:エジプト、ベトナム、カナダ、わからない
第二言語習得では「大量のインプットと少しのアウトプット」ということがよく言われますよね。ソーシャル・メディアで少しのアウトプットを行うには、実際のコミュニティで新しいメンバーを歓迎するコメントをするのがいちばんです。Facebookなどではグループ内の投稿を検索する機能がありますから、「はじめまして」などのキーワードで自己紹介の投稿を検索し、それに歓迎コメントをつけるという課題を出してみましょう。公開コミュニティなら、歓迎コメントをしたページのURLを提出してもらうだけで充分ですが、非公開コミュニティーの場合は「PrintScreen」などで画面を画像としてキャプチャーし、それを提出するという方法が必要になります。
今月はオンラインのコミュニティで新しいメンバーを歓迎する日本語の教え方をご紹介しました。 このように考えてみるとそれほど難しくないのではないかと思います。みなさんの現場でも、ぜひ教室の外の人と繋がるような、こうした活動を取り入れてみてください。
近刊紹介
SNSで外国語をマスターする方法について筆者がまとめた書籍『冒険家メソッド』(ココ出版)が、近日刊行予定!!
《筆者》村上吉文 冒険家。これまで、国際協力機構(JICA)や国際交流基金からモンゴル、サウジアラビア、ベトナム、エジプト、ハンガリーなどへ派遣されてきた。2017年5月からカナダのアルバータ州教育省に勤務。ブログ「むらログ」(http://mongolia.seesaa.net/)では、日本語教育とICTに関する記事や、教育機関によらず自らの力で日本語を学ぶ「冒険家」たちについてのインタビューを発信している。
連載バックナンバー
ソーシャル・メディアをめぐる冒険 第11回 指導例「コミュニティで自己紹介を書くことができる」
ソーシャル・メディアをめぐる冒険 第10回「160文字以内でTwitterのプロフィールを書く」
ソーシャル・メディアをめぐる冒険 第9回「行動中心アプローチとTwitter」
ソーシャル・メディアをめぐる冒険 第8回「日本語教師のためのビデオ会議システム」
ソーシャル・メディアをめぐる冒険 第7回「コミュニティを作ろう」
ソーシャル・メディアをめぐる冒険 第6回「教師自身の学びのために」
ソーシャル・メディアをめぐる冒険 第5回「学習者の安全のために」
ソーシャル・メディアをめぐる冒険 第4回「教師自身が使いこなすために必要な第一歩」
ソーシャル・メディアをめぐる冒険 第3回「自律性と一斉学習」
ソーシャル・メディアをめぐる冒険 第1回「なぜソーシャル・メディアか」
最近の記事
センパイ! 大学院って何をすればいいんですか!? vol.9 webデザイナーのセンパイ