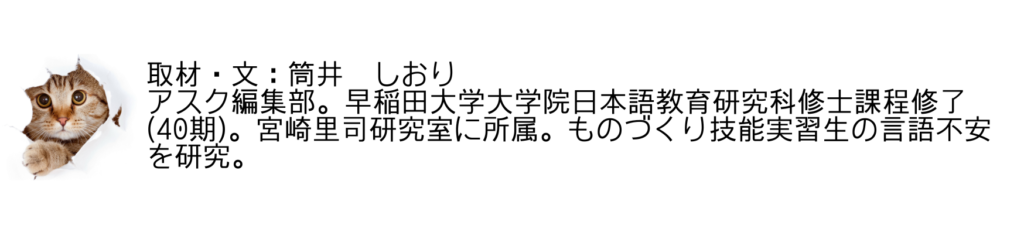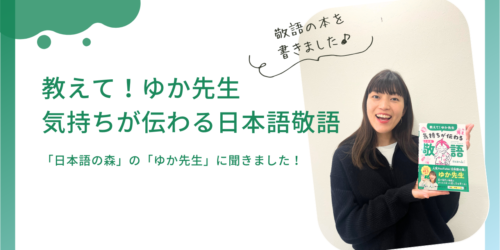同質(sameness)⇔異質(difference)
本記事は【第1回】外国につながる子どもへインタビュー!の続きです。
第1回の記事はこちらから https://www.idobata.online/?p=2948
外国につながる子どもである、高校生のサミさんへインタビューした時の語りから、サミさんのアイデンティティを考察します。本記事では、その語りから表出したアイデンティティをBamberg(2012)の「同質⇔異質」(訳は村田, 2020)を枠組みとして記述します。
自分、日本人じゃないし
サミさんの中学生、高校生の時の交友関係について、抜粋4、5の語りがありました。
私:中学生になって、友だち関係とか、小学生のときと比べて、変わったこととかありましたか?
サミ:最初は、、、やっぱり緊張して、、、自分、日本人じゃないし、なんか話しかけてもいいのかわかんないなーと思ったんです。で、いつもの友だちと同じクラスになったんですね、3人、仲良しの、一緒になったからその3人と一緒にいて、自然とグループ活動とかで自然と仲良くなった子が多かったかな、自分からあんまり話しかけなかったかも。
私:なるほどね。
(抜粋4)
サミさんのいう「いつもの友だち」とは、小学生の時から仲の良かった友だち3人のことです。サミさんとその友だちとの関係については、次回の記事で詳しく述べます。
サミ:しゃべったことない人と、その時は話さなかったです。
私:話したことない人と話せなかった?
サミ:はい、人見知りだったんですよね、当時、そのころは、人見知りで、今はちがうんですけど。
私:へーそうなんだ。スリランカにいるときから人見知りだったんですか?
サミ:こっち(日本)きてから人見知りになったんです。
私:あ、こっち(日本)に来てから人見知りになった。なんでだろう?
サミ:んー環境が変わったからかな、んーあと、なんか自分外国人だしーと思っちゃうんですよね、んー、同じ国の人だったらしゃべれるんですけど、なんか緊張しちゃって
(抜粋5)
抜粋4では、日本人ではない自分、マジョリティとは違う自分が、まわりに話しかけても良いのかわからない、という葛藤があります。そして、抜粋5では、まわりの日本人と話す時に、緊張するとありました。そしてそれは、同国出身の人と話すときには抱かない緊張でした。サミさんは、スリランカ社会では、自分をまわりと同じ「コミュニティのメンバー」として捉え、日本人と話す時に抱くような緊張は感じませんでしたが、一方で、日本社会では、まわりと自分を、日本人か日本人ではないかという点で線引きをし、かつ、自分の立ち位置を「異質」と捉えていたからこそ、話しかけてもよいのであろうか、という気持ちを抱いていました。
こういう時どうするんだっけ
しかし、高校生になり、久しぶりにスリランカに帰ったときに感じた文化の差についての語りからは、サミさんが、以前のような捉え方とは異なる捉え方をしているのではないかと感じました。
サミ:あー最近スリランカに帰った時に、やっぱ礼儀ちがうんです、こっち(日本)と。(私:ふん)んーこっち(日本)だと、誰かの家に行って、飲み物を出されても、全部飲むじゃないですか。でもあっち(スリランカ)だと全部飲まないで、あのちょっと残すんです。全部飲むとまだ欲しいのかなって、注いでくれたりするから、それ飲んじゃったりとかしてました。
私:なるほど。
サミ:そういうのはありました。結構あったかなー、こういう時どうするんだっけっていうのはあります。
私:へー、あ、そうなんだ。で、気づいてどんな感じでしたか、自分飲みほしてるって。
サミ:知り合いだったから大丈夫だったんですけど、全く他人の家に行ったらどうなるんだろーと思っちゃった。
(抜粋6)
知り合いの家に行って、飲み物を出された際、スリランカでは飲み干さないのが礼儀であるとわかってはいたが、サミさんは、つい、日本でしているように、飲み物を飲み干してしまいます。この出来事に対して、サミさんは、「全く他人の家」でそのように飲み干してしまったらどうなっていただろうと思いました。サミさんは、「同質」と捉えているスリランカのコミュニティにて、自分が日本の礼儀に則って、無意識に行動していたことに気づきました。知り合いの家で、失礼にあたることをしてしまった、やってしまった、と焦りを感じたようです。しかし、だからこそ、それが知り合いの家で良かったとも感じています。この語りからは、サミさんが、日本・スリランカ両方のコミュニティのメンバーとして、その場面に相応しいと思う立ち振る舞いをしようとしていることがわかりました。ここにサミさんのもつ複文化性も見えます。
仲よくすれば大丈夫かな
高校での友だちづくりについての語りの中にも、小学生、中学生の時に抱いていた抜粋4,5とは異なる捉え方をしているのが見られました。
私:友だちづくりとかはどうでしたか?
サミ:最初、友だちできるかなーとか思ってたんですけど、意外としゃべれて、できたんですよね、(私:へーよかった)なんか教室のみんな結構、さばさば系?みたいな感じの子が多くて、しゃべりやすかったんです。(私:へー)それで女子はみんな仲良いんです、女子は、(私:わー)なんかうちらの学年でうちらだけらしいんですよね、そんなにみんな仲良いの。
私:へー、めっちゃいいですね。
サミ:男子とはちょっと壁があるけど、男子と交流がなさすぎて、しゃべるときはしゃべるんですけど、そこまでって感じで、中学校とちがって、やっぱちゃんとわかれてるんですよね((笑))
私:へー((笑))でも確かにそうだったかも((笑))
サミ:小学校とか中学校は混ざってたじゃないですか、でも、なんとなくわかれてる。
私:へー、たしかに、私の小学校とか中学校とかも、性別とかなかったかも((笑))でも女子仲良いのはいいですよね。でもなんか、中学校の時に、大人数だったらちょっとしゃべりにくいなーっていうのがあったって。
サミ:なんか、なくなった、そういうの((笑))
私:なくなったの?
サミ:なんか、なくなっちゃった。高校になってから、そういうのしゃべれるようになったんですよね。
私:へー、なんでだろう?
サミ:なんでだろう、多分日本に慣れてきたからかな?
私:ふーん
サミ:(聞き取れない)ですよね、わたし、、、スリランカとかだったら普通に誰でもぐいぐいいけるのに、日本に来てから、あんまりしゃべんなくなったんです。
私:うーん
サミ:外国人だしなんとなく、なんか言われそうで、あんまりしゃべりたくなかったんすよね。(私:ふーん)でもなんか、もういいやって思って((笑))仲よくすれば大丈夫かなって。
(抜粋7)
サミさんは、小学生、中学生の時は、「外国人だし」と、自身をまわりとは「異質」であると解釈していました。そして、「なんか言われそうで、あんまりしゃべりたくなかった」と、話しかけて、傷つくことを避けていました。しかし、高校生になった現在、クラスメートの女子たちを「うちら」と表し、自分と同じコミュニティにいるものとしてくくっています。それから、「なんか言われそうで」しゃべるのを避けていましたが、「なんか、もういいや」「仲よくすれば大丈夫かなって」と「しゃべる」ことを肯定的に捉えなおし、「うちらの学年でうちらだけらしいんですよね、そんなにみんな仲良いの」と、そのコミュニティに誇りをもっています。これらより、自身の立ち位置が、「異質」だったものから「同質」に変容していることがわかります。そこで、サミさんに、以上に述べたような変容をもたらした要因について尋ねました。それに対して、「多分日本に慣れてきたからかな」と答えていました。しかし、「仲よくすれば大丈夫かなって」という語りから、サミさん自身が、クラスメートを受け入れる努力と、自分がクラスメートと良い関係を築く努力を重ねていたことも、変容をもたらした要因の1つではないかと考察します。サミさんがどのようにクラスメートとの関係を築いていったのかは、次回の記事で述べていきます。
以上より、小学生、中学生の時は、自分はまわりと同じではないと感じていましたが、今では同じコミュニティの仲間を誇りに思っていることが見られ、サミさんのアイデンティティに変容がみられました。
参考文献
Bamberg, M. (2012). Why Narrative?. Narrative Inquiry. 22(1). 202-210.
村田和代 (2020)「日本在住日系人へのインタビューナラティブの談話分析」秦かおり・村田和代(編)『ナラティブ研究の可能性―語りが写し出す社会』ひつじ書房.