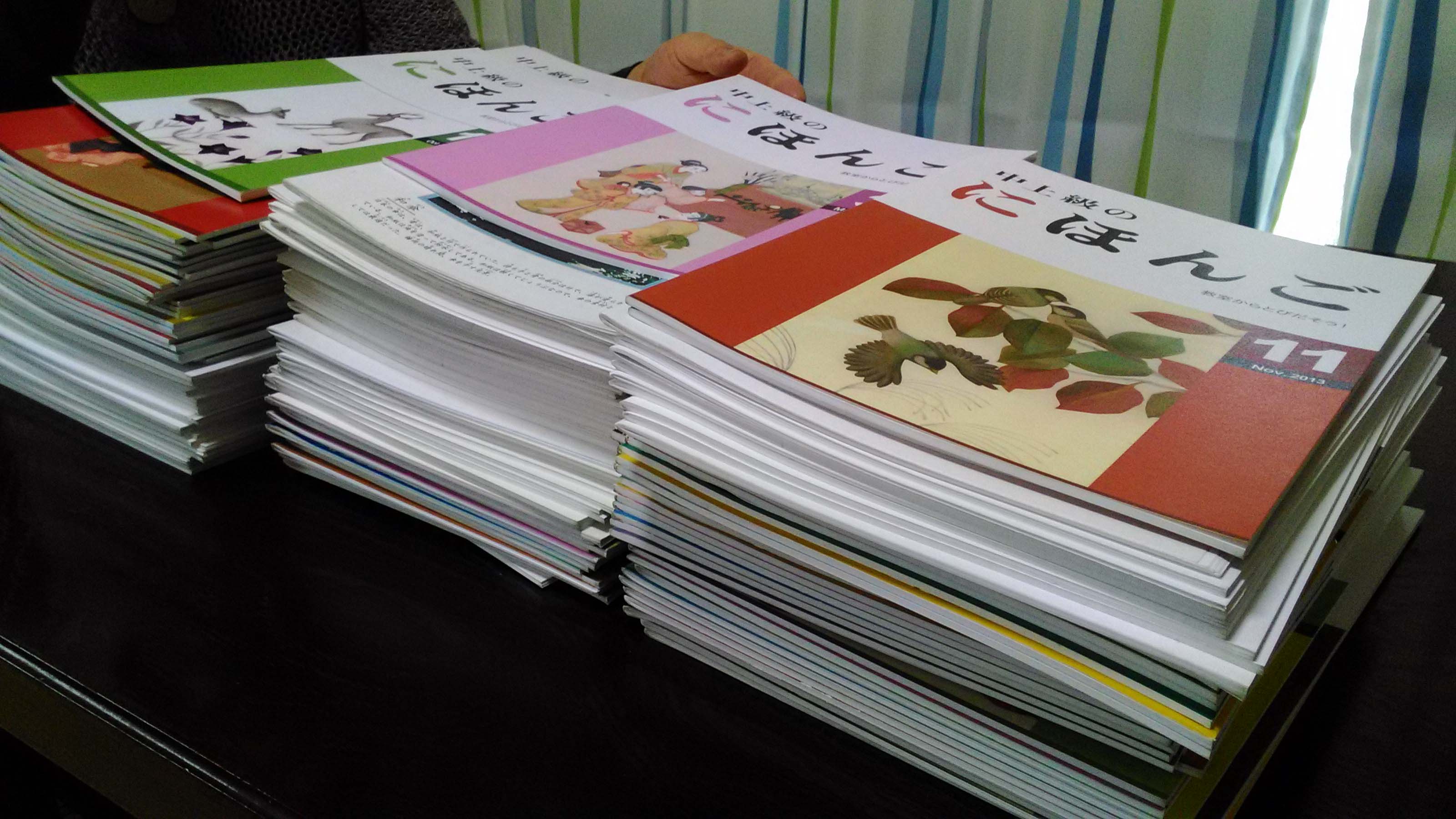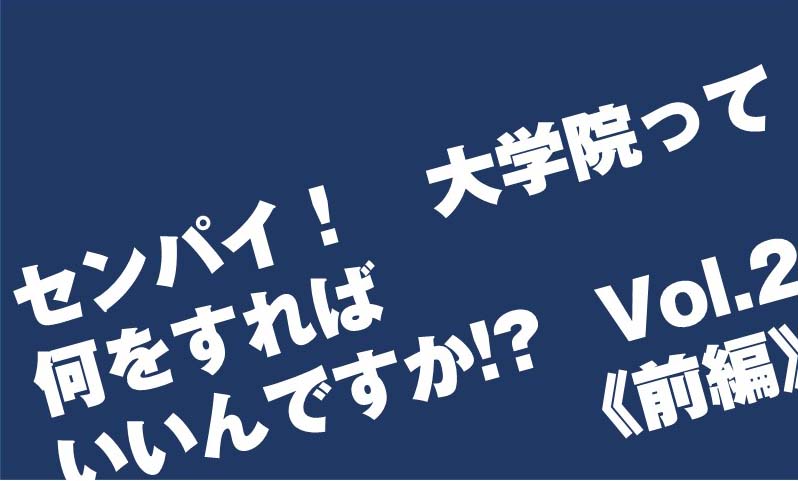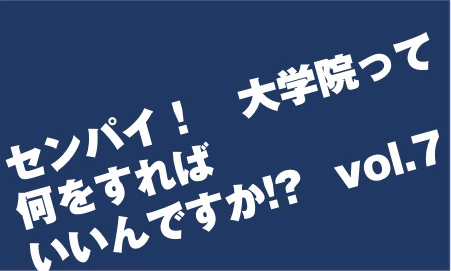連続的⇔非連続的(constancy⇔change)
本記事は【第1,2,3回】外国につながる子どもへインタビュー!の続きです。外国につながる子どもである、高校生のサミさんへインタビューした時の語りから、サミさんのアイデンティティを考察します。
第1回の記事はこちらから https://www.idobata.online/?p=2948
第2回の記事はこちらから https://www.idobata.online/?p=3108
第3回の記事はこちらから https://www.idobata.online/?p=3144
本記事では、その語りから表出したアイデンティティをBamberg(2012)の「連続的⇔非連続的」(訳は村田, 2020)を枠組みとして記述します。村田(2020)は、「連続的⇔非連続的」について
自らの過去と現在との連続性・一貫性を示すことで、私が変わらず私であることを意味することができ、あるいは、非連続性を語ることによって、過去の自らを変化させ、新しい自分になったことを主張することもできる。(p.6)
と述べています。本記事では、以上の「連続的⇔非連続的」において、サミさんの自身の性格が表出しているナラティブを抜粋しながら考察します。
しゃべれなくなる、人見知りになる
サミさんは、スリランカにいた時は、外向的な性格で、自分から人に話しかけることが多かったそうです。しかし、日本に来てまもないころには、スリランカにいた時の自分を出せなくなってしまいました。それについては、サミさんの交友関係についての語りからわかりました。
私:友だちづくりとかはどうですか ?
サミ:最初、友だちできるかなーとか思ってたんですけど、意外としゃべれて、できたんですよね。(私:へーよかった)なんか教室のみんな結構、さばさば系?みたいな感じの子が多くて、しゃべりやすかったんです。(私:へー)それで女子はみんな仲良いんです、女子は。(私:わー)なんかうちらの学年でうちらだけらしいんですよね、そんなにみんな仲良いの。
私:へー、めっちゃいいですね。
サミ:男子とはちょっと壁があるけど、男子と交流がなさすぎて、しゃべるときはしゃべるんですけど、そこまでって感じで、中学校とちがって、やっぱちゃんとわかれてるんですよね((笑))
私:へー((笑))でも確かにそうだったかも((笑))
サミ:小学校とか中学校は混ざってたじゃないですか、でも、なんとなくわかれてる。
私:へー、たしかに、私の小学校とか中学校とかも、性別とかなかったかも((笑))でも女子仲良いのはいいですよね。なんか、中学校の時に、大人数だったらちょっとしゃべりにくいなーっていうのがあったって。
サミ:なんか、なくなった、そういうの((笑))
私:なくなったの ?
サミ:なんか、なくなっちゃった、高校になってから、そういうの。しゃべれるようになったんですよね。
私:へー、なんでだろう。
サミ:なんでだろう、多分日本に慣れてきたからかな。
私:ふーん。
サミ:(聞き取れない)ですよね、わたし…。スリランカとかだったら普通に誰でもぐいぐいいけるのに、日本に来てから、あんまりしゃべんなくなったんです。
私:うーん。
サミ:外国人だしなんとなく、何か言われそうで、あんまりしゃべりたくなかったんすよね。(私:ふーん)でもなんか、もういいやって思って((笑))仲よくすれば大丈夫かなって。
(抜粋 7)
サミさんは、スリランカでは、「誰でもぐいぐいいけ」ていたそうです。「普通に」誰にでも話しかけていたというサミさんは、人と話すということに抵抗がないようでした。しかし、そんなサミさんは、日本にきてから「外国人だし」「何か言われそう」という理由で、以前のサミさんを失ってしまいました。さらに、人見知りにもなってしまったそうです。
私:話したことない人と話せなかった ?
サミ:はい、人見知りだったんですよね、当時、そのころは。人見知りで、今はちがうんですけど。
私:へーそうなんだ。スリランカにいるときから人見知りだったんですか ?
サミ:こっち(日本)きてから人見知りになったんです。
私:あ、こっち(日本)に来てから人見知りになった?なんでだろう。
サミ:んー環境が変わったからかな。(私:んー)あと、なんか自分外国人だしーと思っちゃうんですよね。(私:んー)同じ国の人だったらしゃべれるんですけど。なんか緊張しちゃって。
私:んー。めっちゃわかるなー。私もアメリカにいたときそうだったなー。話しても良いのかなと思っちゃって。でも、不思議じゃないですか、なんでそう思っちゃうんだろう。
サミ:ですね。迷惑かなと思っちゃうんですよね。
私:わかる。私は、英語がへたくそだったから迷惑かなと思って。サミさんはなんでそう思ったんですか。
サミ:中一後半から…ぐらいの時は日常会話とかそういうのは全然大丈夫だったんですけど。大人数が苦手だったし、だからしゃべれなかったのかな。
私:大人数ってどれくらい大人数 ?
サミ:ちょうど良いのが5人くらいかな。テニス部とかがいて、みんな仲良しなんです。あんまり仲良しだと、めっちゃ緊張する。
(抜粋14)
サミさんは「環境が変わった」ことと「自分」が「外国人」であることが、自分を「人見知り」にさせたと感じています。それに対して、私は、自分の経験を思い出しました。私も日本では人見知りもせず、人と話すことが好きでしたが、アメリカで働いていたころ、サミさんと同様に、人見知りになって人に話しかけられなくなったことがありました。私の場合は、他者に自分のカタコト英語を聞いてもらうことへの負担を考え、申し訳ない気持ちになり、人と話すことから逃げていました。そこで、サミさんも私のように思ったのか、質問をしました。しかし、サミさんは、「大人数が苦手」で、他のクラスメートたちがその人たち同士で仲が良い場合、自分が入っていくことを「迷惑かな」と感じたり緊張したりして人見知りになっていました。私は、サミさんの使用できる日本語が制限されていたことが、サミさんを人見知りにしてしまっているのかと思いましたが、日本語は関係なく、誰にでも起こりうる状況で緊張し、人見知りになっていたことがわかりました。サミさんは、現在は以前の自分を取り戻し、「人見知り」することはなくなったそうです。
まとめ
以上のように、本記事では「連続性(constancy)⇔非連続性(change)」を枠組みとして、サミさんのアイデンティティの変容を見てきました。誰にでもぐいぐい話せて、人見知りではなかったサミさんが、日本で生活し始めた小学生のころに、以前とは違うサミさんになっていました。それには、「外国人だから」という理由もありました。一方で、中学生のころは、「大人数が苦手」だという、外見や言語に関係のない、誰にでも抱きうる理由により人見知りになっていました。しかし、現在は以前のような誰とでも話せる、外向的なサミさんを取り戻せました。なぜ取り戻すことができたのかについては、第2, 3回の記事で述べてきたようなコミュニティにサミさんが参加していたからではないかと考えます。
今回の分析を通して、私がサミさんの制限ある日本語面にあまりにも注目しすぎていたことに気づきました。日本語ができなければ、友だちもできず、コミュニティにも参加できず、その上、以前とは異なる自分になってしまうのではないかと思っていました。しかし、サミさんの語りから、それは大きな間違いであるとわかりました。その気づきにより、私の言語観、学習者観が大きく変容しました。
参考文献
Bamberg, M. (2012). Why Narrative?. Narrative Inquiry. 22(1). 202-210.
村田和代(2020)「日本在住日系人へのインタビューナラティブの談話分析」秦かおり・村田和代(編)『ナラティブ研究の可能性―語りが写し出す社会』ひつじ書房.
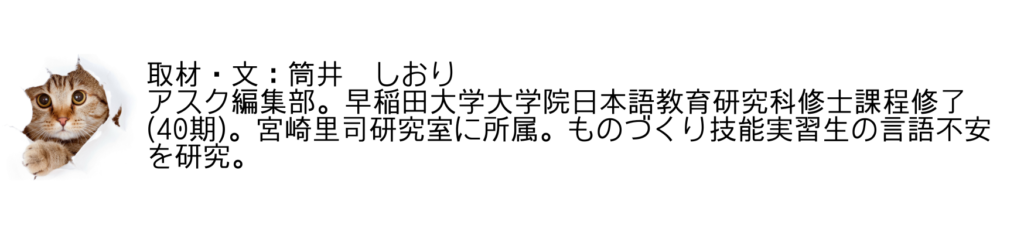
カテゴリー:インタビュー